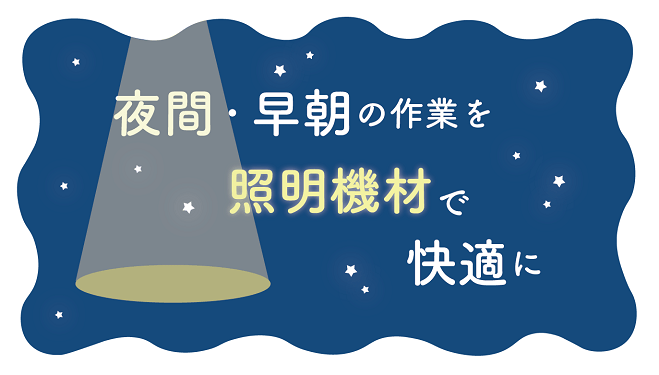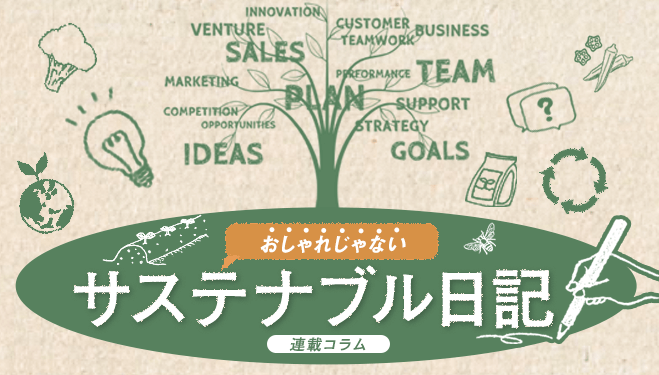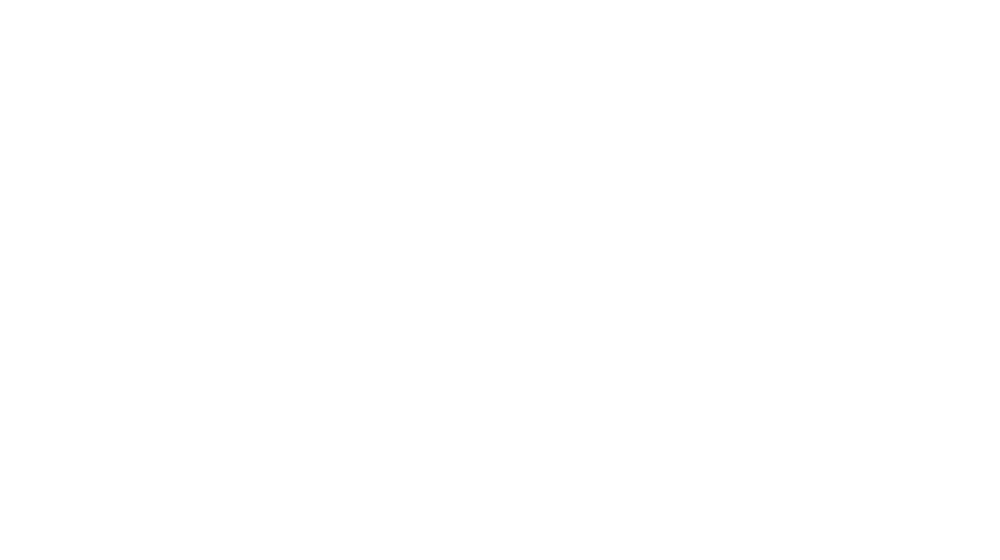目次
月間連載アーカイブはこちら
【毎月更新!】農業なくして持続可能な社会なし今回のテーマ:SDGs目標11|住み続けられるまちづくりを
 今回のコラムと関係するSDGs目標は、【11:住み続けられるまちづくりを】。
今回のコラムと関係するSDGs目標は、【11:住み続けられるまちづくりを】。目標11の内容は「都市と人間の居住地を包摂的(ほうせつてき)、安全、レジリエントかつ持続可能にする」です。
SDGs目標別アーカイブ
目標1・2・3|目標4|目標5|目標6|目標7|目標8|目標10|目標11|目標12|目標13|目標14・15私が「まちづくり」を勉強したかった訳
 「まちづくりの仕事をしています」という自己紹介をされる方に会うと、「それはどーいう仕事なのだ?」と不思議に思ってしまいます。何を隠そう、私が大学に進学したのは、まちづくりの勉強が目的だったのです。厳密に言えば、まちづくりというか都市計画の勉強がしたかったのですが、大きなきっかけは、母の存在とヨーロッパ旅行でした。そのあたりから今回はスタート!
「まちづくりの仕事をしています」という自己紹介をされる方に会うと、「それはどーいう仕事なのだ?」と不思議に思ってしまいます。何を隠そう、私が大学に進学したのは、まちづくりの勉強が目的だったのです。厳密に言えば、まちづくりというか都市計画の勉強がしたかったのですが、大きなきっかけは、母の存在とヨーロッパ旅行でした。そのあたりから今回はスタート!母はバリアフリー建築士
 前回の記事でもご紹介していますが、私の母は1964年の東京パラリンピックがきっかけで、障がいのある方の住まいを専門に設計する仕事に就きました。物心がつく前から車椅子の方の膝に乗せてもらったり、全盲の方にピアノを聴かせてもらったり、いわゆる「五体不満足」の方々に囲まれて育った私は、大きくなるにつれ、彼らの役に立ちたいと思うようになりました。育ててもらったから役に立ちたい、という自然な感情として。
前回の記事でもご紹介していますが、私の母は1964年の東京パラリンピックがきっかけで、障がいのある方の住まいを専門に設計する仕事に就きました。物心がつく前から車椅子の方の膝に乗せてもらったり、全盲の方にピアノを聴かせてもらったり、いわゆる「五体不満足」の方々に囲まれて育った私は、大きくなるにつれ、彼らの役に立ちたいと思うようになりました。育ててもらったから役に立ちたい、という自然な感情として。「自分でできる」ことが増える家づくり
住まいづくりにおいて、障がいはつまり「個性」です。個性に合わせた住まいづくりをすることで、ヘルパーさんに頼むことなく「自分でできること」が増えます。例えば、キッチンを低くすれば車椅子でも料理ができたり、棚を引き戸にすれば自分で棚から物を出し入れしたりすることができます。また家の外でも、花壇を高くすればしゃがめなくても庭仕事ができたり、花は香りの強いものを植えれば、弱視でも花を育てたりすることもできます。家は「非常に高い買い物」ですから、そこに住む人のニーズに合わせてオーダーメイドにするのは当たり前。母のような専門家が入ることで、特殊なニーズにも応えることができ、家主の「限られた力」を伸ばすことができる訳です。パラリンピックの競技を1つでも観た方ならわかると思いますが、特殊な器具やサポートが必要とはいえ、障がいを持っていてもすごい力を発揮できるのです。
車椅子でも生活しやすい工夫がギッシリ
 写真は、母が手掛けた車椅子の方の住宅。2021年の東京パラリンピックでも大いに盛り上がった車椅子バスケットボールですが、1964年の東京パラリンピックにバスケットボール選手として出場した方が施主さんです。一見ごく普通の住宅に見えますが、車いすで生活するための工夫がギッシリ詰まっています。
写真は、母が手掛けた車椅子の方の住宅。2021年の東京パラリンピックでも大いに盛り上がった車椅子バスケットボールですが、1964年の東京パラリンピックにバスケットボール選手として出場した方が施主さんです。一見ごく普通の住宅に見えますが、車いすで生活するための工夫がギッシリ詰まっています。家の外はバリアだらけ
 母の人生を変えた1964年の東京パラリンピックが開催された当時は、「バリアフリー」という言葉、いや、なんなら概念すらありませんでした。それから四半世紀後、私が高校生のときには、「バリアフリー」という言葉こそ一般化してきていましたが、「バリアフリー=スロープや手すり」程度の認識で、街はバリアだらけ。障がいを持っている場合、一歩家の外に出ると、何をするにも苦労するというのが現実でした。
母の人生を変えた1964年の東京パラリンピックが開催された当時は、「バリアフリー」という言葉、いや、なんなら概念すらありませんでした。それから四半世紀後、私が高校生のときには、「バリアフリー」という言葉こそ一般化してきていましたが、「バリアフリー=スロープや手すり」程度の認識で、街はバリアだらけ。障がいを持っている場合、一歩家の外に出ると、何をするにも苦労するというのが現実でした。電動車椅子に乗っている仲の良い友人がいます。普通の車椅子ならまだ大人2人で抱えることも可能なのですが、電動車いすは100キロを超えるので、どうしてもエレベーターがないと移動できません。駅によっては、地方はもちろん、東京でもエレベーターさえないところも未だにあり、まだまだバリアフリーなまちづくりの道のりは先が長いです。
大学で学んだこととドイツ留学へのきっかけ
 私が高校1年生のとき、母がデンマークまで重度障がい者施設を見に行くというので、それに同行しました。そのときに受けた、大きな大きなカルチャーショックを一生忘れることはないでしょう。
私が高校1年生のとき、母がデンマークまで重度障がい者施設を見に行くというので、それに同行しました。そのときに受けた、大きな大きなカルチャーショックを一生忘れることはないでしょう。目も見えない、耳も聞こえない、歩くこともできない、ヘレンケラーのような障がいを持った方の部屋を見せてもらったときのこと。部屋は美しくデコレーションが施され、絵や花が飾ってありました。そこで働くヘルパーさんが言うには、「本人は見えなくても、きっと何かを感じ取ることができるし、周りのヘルパーたちが話題にもできるから、季節ごとに模様替えもするのよ」とのことでした。
日本では、全盲の方の施設は病院並みの白一色なのが当たり前でしたから、その施設の中の様子に身震いするほど感動し、その後の私に大きな影響と夢を与えてくれました。「これが共存なんだ!」と。そして、家づくりは母に任せ、私はまちづくり(都市計画)でバリアフリーを目指したい!と思うようになったのです。
とはいえ、高校まではエスカレーターで進学できたこともあり、バスケや遊びが中心で、じっと机に向かって勉強するのがとても苦手だった私。受験を早々に諦め、「人にも自然にも優しいまちづくり」の仕事を目指して、自己推薦枠で大学に進学。高い学費を出してもらって私立大学に入学しましたが、勉強したい目的がはっきりしていたので、学費分はしっかり勉強したという自負があります!高校までにしっかり遊んでおく、というのは割と大事なのかもしれません(笑)。
バブル時代の都市計画にモヤモヤ
 ところが、です。バブル経済はとっくに弾けてしまっていた1994〜1998年当時。大学の授業は、バブル経済を牽引(けんいん)してきたような方々による、アメリカを向いた経済論や大型開発を前提とした都市計画論など、バブル時代の名残りが色濃い内容でした。
ところが、です。バブル経済はとっくに弾けてしまっていた1994〜1998年当時。大学の授業は、バブル経済を牽引(けんいん)してきたような方々による、アメリカを向いた経済論や大型開発を前提とした都市計画論など、バブル時代の名残りが色濃い内容でした。ゼミの課題も、効率性・経済性を重視した「ニュータウン」の計画や駅前再開発、高層マンションのコミュニティづくりなどで、私はもちろん「バリアフリー」という観点から取り組みましたが、卒業するまでモヤモヤ感を持ち続けていました。
結果的に、そのモヤモヤのおかげでドイツの大学院に進学することにしたわけで、ドイツで目の当たりにした「持続可能な社会を目指す姿」が今の私の原点になっているので、大学時代は何も無駄ではなかったと思っています。むしろ、その後結婚することになるパートナーを見つけただけでも、大学に行ったかいはあったと(笑)。
気の遠くなるようなドイツのまちづくりのプロセス
 20年前のドイツでは、今のSDGsの前身ともいえる、「Agenda21」と呼ばれる「持続可能な開発や発展を目指した国際的な目標をどうやってまちづくりの中で目指すのか」という課題に取り組んでいて、そこから具体的なヒントをたくさん得ることもできました。
20年前のドイツでは、今のSDGsの前身ともいえる、「Agenda21」と呼ばれる「持続可能な開発や発展を目指した国際的な目標をどうやってまちづくりの中で目指すのか」という課題に取り組んでいて、そこから具体的なヒントをたくさん得ることもできました。「まちづくり」は基本的に、自治体が主となって土木や建設の専門家が計画をつくります。でもそれだと、実際にそこに住んでいる人の視点や要望がきちんと反映されないよね、ということで、当時のドイツでは、計画づくりの段階から住民も参加するようになっていました。
ドイツは労働者組合が生まれた国でもある通り、市民の声が強い国。ただ、市民の声にあおられてナチス政権が台頭してしまったという過去もあり、過ちを繰り返してはいけない、という意識の高さも感じました。
まちづくりのための重要な仕事とは?
 住民のニーズは多様です。不便だから道路を作れという住民もいるかと思えば、そこに道路はいらないという住民もいる。あーでもない、こーでもない、という住民たちが計画作りに参加するわけですから、技術系の専門家さんでは手に負えない。人をまとめるのは土木や建設の技術とは別次元ですから。
住民のニーズは多様です。不便だから道路を作れという住民もいるかと思えば、そこに道路はいらないという住民もいる。あーでもない、こーでもない、という住民たちが計画作りに参加するわけですから、技術系の専門家さんでは手に負えない。人をまとめるのは土木や建設の技術とは別次元ですから。そこで、「住み続けられるまち・むら」の将来像を描くために、ワークショップや住民説明会を何度も開き、とてつもない時間をかけてなるべく多くの住民が納得する計画にしていくための、ファシリテーターやモデレーターという職業が誕生しました。これが今、日本でも耳にする「まちづくりの仕事をしています」という職種なんじゃないかなと、私は思っています。
「まち」じゃなくて「むら」に住んじゃった
 ドイツでの「住み続けられるまちづくり」の学びはとても興味深く、大学で抱いていたモヤモヤ感は解消しました。「そうか、障がいを持つ人も計画づくりに参加してもらって、長い時間をかけてでも、より住みやすいまちをつくりあげていけばいいんだ!」と意気揚々と帰国したものの、そんな仕事に就く前に夫の郷里で就農することに。
ドイツでの「住み続けられるまちづくり」の学びはとても興味深く、大学で抱いていたモヤモヤ感は解消しました。「そうか、障がいを持つ人も計画づくりに参加してもらって、長い時間をかけてでも、より住みやすいまちをつくりあげていけばいいんだ!」と意気揚々と帰国したものの、そんな仕事に就く前に夫の郷里で就農することに。多少の心残りはありましたが、南阿蘇という世にも美しい景観の村に引っ越すことへのワクワク感が大きく、私は迷いもせずに東京を離れました。そして村での暮らしが始まったのです。
住み続けられる「むらづくり」を目指して
 「増田レポート」とも呼ばれる『地方消滅 – 東京一極集中が招く人口急減』という、中公新書の出版物が世に出たのは2014年。さまざまな議論を呼び起こした内容で「消滅」という響きもショッキングですが、2003年に農村に移住し、超高齢社会のど真ん中にいる私としては、「このままだと本当に誰もいなくなっちゃうかも」と感じたことは、一度や二度じゃありません。
「増田レポート」とも呼ばれる『地方消滅 – 東京一極集中が招く人口急減』という、中公新書の出版物が世に出たのは2014年。さまざまな議論を呼び起こした内容で「消滅」という響きもショッキングですが、2003年に農村に移住し、超高齢社会のど真ん中にいる私としては、「このままだと本当に誰もいなくなっちゃうかも」と感じたことは、一度や二度じゃありません。そんな中、4人の子どもを産んで、農村の人口減少に微力ながら貢献している貴重な(?)立場の私だからこそ、住み続けるむらとは?という問いを立てて考えてみたいと思います。
農家の数が減るより、農村の人口が減ることが問題
 農家の数が減少の一途をたどっていることは、農業関係者じゃなくても想像のつく話です。この先、昭和一桁世代が引退したら、いったいこの国の農地や農業はどうなってしまうのだろう、と思います。
農家の数が減少の一途をたどっていることは、農業関係者じゃなくても想像のつく話です。この先、昭和一桁世代が引退したら、いったいこの国の農地や農業はどうなってしまうのだろう、と思います。農業者数は減っているものの、法人は増えているので、サラリーマンとして農業に従事している人は増えている、と農水省はデータを出しています。でも、農業者の数が減ることよりも、非農家も含めた農村の人口が減っていくのは今のところ手の打ちようがなく、とても心配な状況です。
ちなみに、双子の長男と次男が小学校に入学したときは、新入生が4人で、そのうち2人が我が家の息子!でした。全校生徒が40人弱でアットホームな小学校でしたが、ついに今年の3月で閉校しました。
空き家率が3割を超えると一気に増える、といわれていますが、それと同じで、農村の人口が減ると行政サービスも行き届かなくなり、コミュニティも崩壊するので、人口の減少が一気に加速してしまうように思います。現に、熊本地震で大学のキャンパスを失った南阿蘇村は、観光地である人気のエリアも含めて人口減少に歯止めがかかりません。
10年後、20年後、30年後も住み続けるために
 じゃあ何をすればいいかという答えはどこにもありません。ただ、水も空気も美しく、風光明媚(ふうこうめいび)な南阿蘇村に心底ほれている私としては、なんとかしてここを住み続けられる場所にしたいという思いは日々抱いています。
じゃあ何をすればいいかという答えはどこにもありません。ただ、水も空気も美しく、風光明媚(ふうこうめいび)な南阿蘇村に心底ほれている私としては、なんとかしてここを住み続けられる場所にしたいという思いは日々抱いています。農業体験はもちろんのこと、しめ縄や竹細工のワークショップや食育イベントなど、友人たちやお米を買ってもらっているお客さんや学生さんたちが、「行ってみたい!」と思うようなイベントや仕掛けもたくさん手がけてきました。
 稲刈りが終わった後の田んぼで期間限定のカフェを数年間続けていたとき、「こうやって、地元の人が気軽にお茶を飲みに来れるところがあればいいのに」という声を受けて、熊本地震発災の年に「コミュニティカフェ」をオープン。村の資源として、木や草を使ったエネルギー供給の取り組みや、コロナ禍では、授業がオンライン化した大学生たちを受け入れ、「休学しない農村留学」を実証しました。まぁそれはいろいろと、思いつく限りのことをやってきています。
稲刈りが終わった後の田んぼで期間限定のカフェを数年間続けていたとき、「こうやって、地元の人が気軽にお茶を飲みに来れるところがあればいいのに」という声を受けて、熊本地震発災の年に「コミュニティカフェ」をオープン。村の資源として、木や草を使ったエネルギー供給の取り組みや、コロナ禍では、授業がオンライン化した大学生たちを受け入れ、「休学しない農村留学」を実証しました。まぁそれはいろいろと、思いつく限りのことをやってきています。ここに住みたい!と思う仲間を増やすこと
 悪あがきともいえるさまざまな取り組みをしてきたのが、成功だったのか失敗だったのかはわかりません。でも結果として、私たちの存在がきっかけとなって東京から移住してきたのが17人。その彼らが全員、結婚と出産をして、今では35人にもなりました。
悪あがきともいえるさまざまな取り組みをしてきたのが、成功だったのか失敗だったのかはわかりません。でも結果として、私たちの存在がきっかけとなって東京から移住してきたのが17人。その彼らが全員、結婚と出産をして、今では35人にもなりました。私はここが好きで満足している
 私は決して「ぜひ住みにおいでよ!」とは誘いません。何人か移住してきても、人口減少が食い止められるほど現実は甘くなく、移住したはいいものの、「住みにくい」状況になるかもしれないからです。
私は決して「ぜひ住みにおいでよ!」とは誘いません。何人か移住してきても、人口減少が食い止められるほど現実は甘くなく、移住したはいいものの、「住みにくい」状況になるかもしれないからです。ただ、「私はここが好きで満足している」と伝えます。これは本心です。今年もまた、4月から20代女子がその言葉にひかれてやって来てくれました。彼女はシェアハウスを近々始めるとのことなので、きっと彼女の仲間も増えていくことでしょう。
義理の祖父母のありがたさ
 義理の祖父母が生きていたころは、義祖父が竹林や山の整備をして薪でお風呂を沸かしてくれ、義祖母がお漬物やおまんじゅうを作ってくれ、私たち夫婦は農業をしながら、農村でしかできないのびのび子育てを楽しんでいました。
義理の祖父母が生きていたころは、義祖父が竹林や山の整備をして薪でお風呂を沸かしてくれ、義祖母がお漬物やおまんじゅうを作ってくれ、私たち夫婦は農業をしながら、農村でしかできないのびのび子育てを楽しんでいました。義祖父母が他界して、菜園や山の手入れが疎かになり、農業+育児で忙し過ぎて、季節を楽しむ暮らしができずにいる今日このごろ。それでも忙しい1日を終えて、子どもたちと一緒に満天の星空を見たり、暑い日は水源や川に遊びに行ったりと、楽しみはたくさんあります。ただ、高校生になると村から出ていく子も多く、それに伴って出費も増えるので、なかなか悠々自適というわけにはいきませんが。
三人寄れば文殊の知恵
 望んで産んだ子どもたちがいるからには、子どもたちにこの美しい村をのこしていきたい。そのためには、私たちが諦める訳にいきません。まずは農業を続けること。そして農村の魅力を発信していくこと。仕方なく農村に住んでいるのではなく、自然豊かな農村にこそ住みたいと思う仲間を増やすこと。
望んで産んだ子どもたちがいるからには、子どもたちにこの美しい村をのこしていきたい。そのためには、私たちが諦める訳にいきません。まずは農業を続けること。そして農村の魅力を発信していくこと。仕方なく農村に住んでいるのではなく、自然豊かな農村にこそ住みたいと思う仲間を増やすこと。三人寄れば文殊の知恵、ということで、人が集まればきっと次のやりたいことが見えてくると思っています。移住してできた仲間たちと3人で、地元のお祭りに出店し、いわゆる「地産地消」の走りのような手作りお菓子を販売したのも今では良い思い出です。
「まちづくりの仕事」にこそ就きませんでしたが、自分たちがこの地に住み続けるためにも、諦めずに人にも自然にも優しい「むらづくり」を目指していくつもりです。
大津愛梨さんのコラムアーカイブはこちら
【毎月更新!】農業なくして持続可能な社会なし家族経営農家の生活を写真と共に紹介♪「ハッピーファミリーファーマーズ日記」
大津 愛梨(おおつ えり)プロフィール
1974年ドイツ生まれ東京育ち。慶応大学環境情報学部卒業後、熊本出身の夫と結婚し、共にミュンヘン工科大学で修士号取得。2003年より夫の郷里である南阿蘇で農業後継者として就農し、有機肥料を使った無農薬・減農薬の米を栽培し、全国の一般家庭に産直販売している。
女性農家を中心としたNPO法人田舎のヒロインズ理事長を務めるほか、里山エナジー株式会社の代表取締役社長、一般社団法人GIAHSライフ阿蘇の理事長などを兼任。日経ウーマンの「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」やオーライニッポン「ライフスタイル賞」のほか、2017年には国連の機関(FAO)から「模範農業者賞」を受賞した。農業、農村の価値や魅力について発信を続けている4児の母。
ブログ「o2farm’s blog」