目次
-
- AGRI PICK 編集部
AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む
農家の収入はどのくらい?

収入と所得の違い
農業で稼げる金額について知る前に、収入と所得は違うということをチェックしておきましょう。収入というのは「入ってくるお金」のこと。所得というのは「収入から必要経費を差し引いたもの」です。
農業法人などの社員として働く場合には、給与が支給されることになるので、給与明細を見れば支給と控除の欄があり、収入と所得の差がわかりやすいですね。
自分で独立して農業経営をする場合には、農作物の販売金額など農業経営の成果として入ってきたお金は「収入」となり、この収入を得るために必要な土地代、資材や肥料などの経費を差し引いたものが「所得」となります。
農業所得平均「191万円」の現実
農林水産省が行っている農業経営統計調査にによると、2017年度の農業経営体(個別経営)の1経営体当たりの農業粗利益は623万円、農業経営費は433万円で、農業粗利益から農業経営費を差し引いた農業所得は191万円。これに農産加工、農家民宿、農家レストラン、観光農園などで収益を上げた農業生産関連事業所得や、地代収入や利子などの農外収入、年金等を加えた総所得は526万円となっています。業種によって開きも。安定した所得を得る難しさ
業種によって所得には大きな開きがあります。営農類型別経営統計(個別経営編)(2017年、単位:万円、前年比のみ%)
| 営農類型 | 農業粗利益 | 農業経営費 | 農業所得 | 前年比 |
| 水田作 | 277 | 207 | 70 | +11.2% |
| 畑作 | 954 | 606 | 348 | +29.6% |
| 露地野菜 | 602 | 368 | 234 | △3.9% |
| 施設野菜 | 1,250 | 743 | 507 | △8.2% |
| 果樹作 | 594 | 368 | 226 | △8.5% |
農業所得が最も多いのは施設野菜です。施設野菜は、他の業種に比べて施設を作るための初期投資や燃料費などが必要ですが、成功すれば所得も大きくなります。
また、前年比を参照すると、2017年度、施設野菜についてはトマト等の主要品目の価格が前年よりも落ち着いたことなどから減少したこと、果樹作については、生育期間中の天候不順や台風等の影響により、リンゴやカキの果実品質が低下したことにより価格が下落したとみられています。農業で安定した所得を得ることが難しいことがわかります。
農業所得で生活していけるのか?
農業所得で生計を成り立たせている新規参入者も
果たして、農業だけで生活していけるのかという疑問がわいてきますね。2018年度に全国新規就農相談センターが行った「新規参入者の経営資源の確保に関する調査結果」によると、新規参入者が農業所得で生計が成り立っているかについて「おおむね農業所得で生計が成り立っている」との回答が43.2%、「農業所得では生計は成り立たない」が56.8%でした。農業所得で生活を成り立たせるには努力と工夫が必要であるといえますが、まったく不可能というわけではありません。また、国も新たに農業に従事する人を支援しています。就農直後の経営確立を支援する資金を交付してくれる「農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)経営開始型」を受給することができれば、スタート時の大きな助けとなります。
専業農家は意外と少ない
 全国の農家数は215万5千戸で、このうち経営耕地面積が30a以上または1年間における農産物販売金額が50万円以上の販売農家数は133万戸となっています。このうち、 農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる主業農家は29万4千戸に過ぎません。農業だけで生活をしている農家というのは、かなり少ないといえるのです。
全国の農家数は215万5千戸で、このうち経営耕地面積が30a以上または1年間における農産物販売金額が50万円以上の販売農家数は133万戸となっています。このうち、 農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる主業農家は29万4千戸に過ぎません。農業だけで生活をしている農家というのは、かなり少ないといえるのです。参考:2015年農業センサス
主業農家とそれ以外の農家では、所得にも開きが見られます。主業農家の農業所得の全国平均は約668万円であるのに対し、それ以外のいわゆる兼業農家は約61万円に過ぎません。
参考:2017年農業経営統計調査
脱サラ前に副業で!週末農業で得る収入とは?
 将来的に農業を主な収入源にしたいと考えても、初めて農業をする人がいきなりサラリーマンなどの現在の仕事を辞めて、農業だけの収入で生活しようとするのはリスクが高いです。また、就農前に就農に必要な資金や当面の生活費を貯蓄しておく必要もあります。
将来的に農業を主な収入源にしたいと考えても、初めて農業をする人がいきなりサラリーマンなどの現在の仕事を辞めて、農業だけの収入で生活しようとするのはリスクが高いです。また、就農前に就農に必要な資金や当面の生活費を貯蓄しておく必要もあります。そこで、まずは「週末農業」「副業」という形で農業に携わるという方法もあります。身近に週末農業ができるレンタル農園や市民農園があるか調べてみましょう。このような農園には野菜作りを教えてくれる指導員がいる場合があり、初めて農業をする人には参考になる情報を得られることも。
また、本格的な就農前の助走期間として自分や家族の食べる野菜を作ることは、家計にもメリットがあります。週末農業でどのくらい稼げるのかについて、公の情報はありませんが、多くは直売所に出荷したり、ネット販売をするなどして得るお小遣い稼ぎレベルのものが多いようです。
東京23区の市民農園情報はこちら
週末農業では物足りない場合には、農業研修に参加することも一つの方法です。収入を得ながら農業の技術を学ぶことができる研修もあります。
農業研修についての記事はこちら
農業所得は確定申告が必要
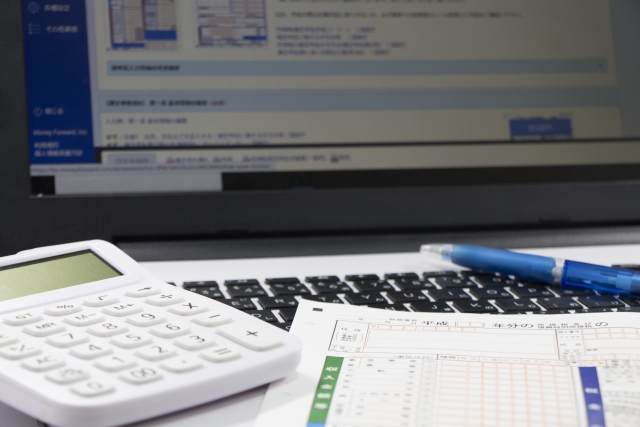
白色申告と青色申告の違い
個人事業として農業を営むなら、確定申告を行う必要があります。申告には、白色申告と青色申告があり、白色申告は原則的な申告方法です。それに対し、青色申告は一定水準以上の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人について、税務署長から承認を受けて、最高65万円が控除されたり、配偶者やその他の親族へ支払った給与を必要経費に算入できるなどの有利な取り扱いが受けられる制度です。青色申告を行うためには、その年の3月15日まで(1月16日以後に新規に業務を開始した場合には2カ月以内)に納税地の税務署長に届出を行います。青色申告もソフトを使えば難しくない!
青色申告については、帳簿をつけることが難しいのではという懸念があるかもしれませんが、必要な項目を入力すれば自動で帳簿を作成することができるソフトがあるので、白色申告と大きな違いはなくなってきています。収入については、農産物の収穫、農産物等の売上・家事消費、雑収入等を記載する必要があります。雑収入とは空袋、稲わらなどの売却代金や受取共済金などを指します。参考:「帳簿の記帳のしかたー農業所得者用-」
農業用の青色申告のためのソフトについてはこちら
農業所得は工夫次第で上げられる
 いずれは農業だけで生活をしていきたい場合、どのようにして農業所得を上げていけばいいのでしょうか。いくつかのポイントをチェックしてみましょう。
いずれは農業だけで生活をしていきたい場合、どのようにして農業所得を上げていけばいいのでしょうか。いくつかのポイントをチェックしてみましょう。1. 価格競争を避ける
 「同じものなら安いものを買いたい」これが消費者の心理です。農業も同じで、同じ作物を作る人がたくさんいれば、価格競争が発生します。価格競争に巻き込まれないことが所得を上げる一つの手段です。その方法として、他の人があまり作らない品種を作る、安心や味などの付加価値をつける、嗜好用や観賞用など特徴的な作物を作ることなどが考えられます。
「同じものなら安いものを買いたい」これが消費者の心理です。農業も同じで、同じ作物を作る人がたくさんいれば、価格競争が発生します。価格競争に巻き込まれないことが所得を上げる一つの手段です。その方法として、他の人があまり作らない品種を作る、安心や味などの付加価値をつける、嗜好用や観賞用など特徴的な作物を作ることなどが考えられます。希少性の高い野菜を作り、収益を上げているタケイファームの記事はこちら
2. 自分の顧客を確保する
 卸を省き、自分独自の顧客を持つことで、所得を向上させる方法があります。例えば、自分の作った野菜を家庭に直接宅配する、レストランに販売するなどが考えられます。顧客を得るためには、営業活動が必要ですが、ITやSNSの活用など方法はいろいろあります。また、発想を転換し、観光農園や農業体験など、「モノ」ではなく「コト」を提供するビジネスにすることもできます。
卸を省き、自分独自の顧客を持つことで、所得を向上させる方法があります。例えば、自分の作った野菜を家庭に直接宅配する、レストランに販売するなどが考えられます。顧客を得るためには、営業活動が必要ですが、ITやSNSの活用など方法はいろいろあります。また、発想を転換し、観光農園や農業体験など、「モノ」ではなく「コト」を提供するビジネスにすることもできます。出荷の95%がレストランというタケイファームの記事はこちら
農家と消費者をつなぐネット通販サービスについての記事はこちら
3. コストを削減する
 所得を上げる方法というと、売り上げを上げることを考えがちですが、同じくらい大切なことはコストの削減です。特に農業機械には大きなコストがかかるため、「機械化貧乏」とならないように、中古の機械を購入して取得コストを抑えることや、アタッチメントを付け替えることで複数の用途に利用できる機械を利用することなどが有効です。また、肥料は土壌の成分分析をすることで必要最低限の量を使用する、資材の購入は共同購入や現金一括払いなどをするなど、削減できるコストがないか常に意識することが所得の向上につながります。
所得を上げる方法というと、売り上げを上げることを考えがちですが、同じくらい大切なことはコストの削減です。特に農業機械には大きなコストがかかるため、「機械化貧乏」とならないように、中古の機械を購入して取得コストを抑えることや、アタッチメントを付け替えることで複数の用途に利用できる機械を利用することなどが有効です。また、肥料は土壌の成分分析をすることで必要最低限の量を使用する、資材の購入は共同購入や現金一括払いなどをするなど、削減できるコストがないか常に意識することが所得の向上につながります。4. ITの活用
 コストを削減するためには、コストがいくらかかっているか、正確に把握する必要があります。そのような場面で役に立つのがITツールです。どれだけの種をまき、肥料や農薬を使ったのか。また各作業に要した人手と時間などをデータベース化して管理することで、より良い経営につなげることができます。ほかにも土壌を調べるセンサーやハウス内の温度、湿度、照度を把握するための環境センサーなどのITツールを使うことで、余計な手間やコストを削減することができます。
コストを削減するためには、コストがいくらかかっているか、正確に把握する必要があります。そのような場面で役に立つのがITツールです。どれだけの種をまき、肥料や農薬を使ったのか。また各作業に要した人手と時間などをデータベース化して管理することで、より良い経営につなげることができます。ほかにも土壌を調べるセンサーやハウス内の温度、湿度、照度を把握するための環境センサーなどのITツールを使うことで、余計な手間やコストを削減することができます。営農管理アプリについてはこちら
自然災害などのリスクは収入保険でカバー
 2019年1月から収入保険がスタートしました。これは、全ての農産物を対象とし、農業経営者ごとの収入に総合的に対応した保険で、自然災害や農産物の価格の下落などで売上が減少した場合に、その減少分の一部が補償されるものです。青色申告の実績が1年分あれば加入でき、けがや病気で収穫ができない場合や、収穫後の保管中の事故、為替変動による売上減少の際に、平均収入の8割以上の収入が確保できるというメリットがあります。また、損害がなければ翌年の保険料率が下がります。一方、デメリットは、保険料という固定費がかかること。災害などの発生頻度が低く、少量多品目栽培などで、一度に大きな損失を受けにくい場合には保険料を無駄に感じる場合もあるでしょう。詳しくは農林水産省ホームページを参照するか、地域の農業共済組合に問い合わせてみましょう。
2019年1月から収入保険がスタートしました。これは、全ての農産物を対象とし、農業経営者ごとの収入に総合的に対応した保険で、自然災害や農産物の価格の下落などで売上が減少した場合に、その減少分の一部が補償されるものです。青色申告の実績が1年分あれば加入でき、けがや病気で収穫ができない場合や、収穫後の保管中の事故、為替変動による売上減少の際に、平均収入の8割以上の収入が確保できるというメリットがあります。また、損害がなければ翌年の保険料率が下がります。一方、デメリットは、保険料という固定費がかかること。災害などの発生頻度が低く、少量多品目栽培などで、一度に大きな損失を受けにくい場合には保険料を無駄に感じる場合もあるでしょう。詳しくは農林水産省ホームページを参照するか、地域の農業共済組合に問い合わせてみましょう。幅広い知識を得て、農業で生計を立てよう
 農業で収入を上げるためには、まずは品質の良い農作物をたくさん生産する、というのは当然のこと。ほかでは作れないような高品質な農作物を生産することに専念して、高収入を得ることも一つの方法です。ただ、継続的に収入を得ていくためには、品目選び、ブランディング、販売先の確保、コストの削減、保険や税など、幅広い知識が必要になってきます。収入を得られることが、農業を継続するための第一歩。自分ならではの工夫で生計を立てられる農業を目指しましょう。
農業で収入を上げるためには、まずは品質の良い農作物をたくさん生産する、というのは当然のこと。ほかでは作れないような高品質な農作物を生産することに専念して、高収入を得ることも一つの方法です。ただ、継続的に収入を得ていくためには、品目選び、ブランディング、販売先の確保、コストの削減、保険や税など、幅広い知識が必要になってきます。収入を得られることが、農業を継続するための第一歩。自分ならではの工夫で生計を立てられる農業を目指しましょう。




























