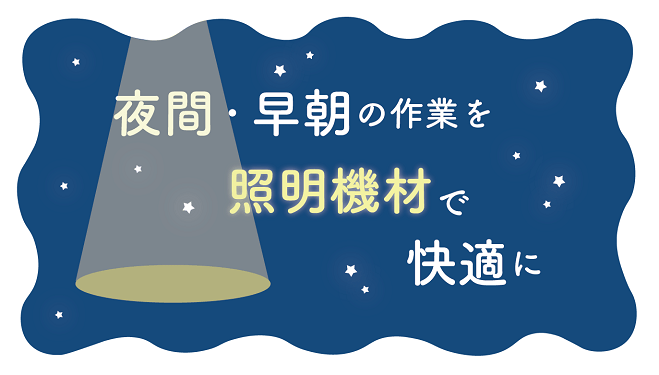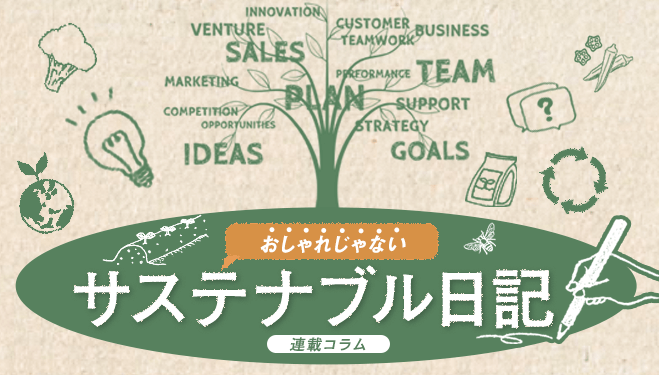-
気象予報士
寺本 卓也1985年1月4日生まれ。東京都出身。 東京農業大学卒業後、青果業で社員として勤務。2018年秋に気象予報士の資格を取得。 株式会社ウェザーマップ所属。テレビユー福島「Nスタ ふくしま」に出演中。…続きを読む
そんな農家にとって「大敵」ともいえる霜害の発生要因と対策についてご紹介します。
霜害について気象予報士にインタビュー
霜害を理解する上での基本情報と、農作物被害を防ぐ方法について、気象の専門家である気象予報士の寺本卓也さんにお話を伺いました。 株式会社ウェザーマップ所属の気象予報士、寺本卓也さん。気象予報士になる前は野菜を扱う商社で仕事をしていました。天気による農作物への影響や気象データの利用方法について、詳しく教えてくださいました。
株式会社ウェザーマップ所属の気象予報士、寺本卓也さん。気象予報士になる前は野菜を扱う商社で仕事をしていました。天気による農作物への影響や気象データの利用方法について、詳しく教えてくださいました。寺本卓也さんプロフィール
1985年1月4日生まれ。東京都出身。
東京農業大学卒業後、青果業で社員として勤務。2018年秋に気象予報士の資格を取得。
株式会社ウェザーマップ所属。テレビユー福島「Nスタ ふくしま」に出演中。
霜害(凍霜害)とは?
 そもそも、霜害とはどのような状態のことを指すのでしょうか?
そもそも、霜害とはどのような状態のことを指すのでしょうか?
寺本卓也さん
寒さで空気中の水蒸気が冷えて凍り、地表におりた状態を「霜(しも)」といいます。
この霜によって野菜や果樹が凍結して枯れてしまったり、傷んでしまったりすることを霜害(そうがい)といい、低温によって作物が凍る「凍害(とうがい)」とあわせて凍霜害(とうそうがい)ともいいます。
気象庁では、発生する時季によって霜を「早霜(はやしも)」「遅霜(おそじも)」という言葉を使って表します。早霜は秋の季節外れに早い冷え込みで起こる霜のこと、遅霜は晩春におりる霜のことを指します。早霜が起こると秋の収穫物である柿やりんごの実に傷みが生じ、遅霜が起こると桃やりんごの花が枯れて実が付かなくなってしまうことがあります。
この霜によって野菜や果樹が凍結して枯れてしまったり、傷んでしまったりすることを霜害(そうがい)といい、低温によって作物が凍る「凍害(とうがい)」とあわせて凍霜害(とうそうがい)ともいいます。
気象庁では、発生する時季によって霜を「早霜(はやしも)」「遅霜(おそじも)」という言葉を使って表します。早霜は秋の季節外れに早い冷え込みで起こる霜のこと、遅霜は晩春におりる霜のことを指します。早霜が起こると秋の収穫物である柿やりんごの実に傷みが生じ、遅霜が起こると桃やりんごの花が枯れて実が付かなくなってしまうことがあります。
霜害(凍霜害)が起こるメカニズム
 農作物に大きな被害をもたらす霜害は、どのような場所で、どのような気象条件のときに起こりやすいのでしょうか。霜害が起こるメカニズムについて、寺本さんに聞きました。
農作物に大きな被害をもたらす霜害は、どのような場所で、どのような気象条件のときに起こりやすいのでしょうか。霜害が起こるメカニズムについて、寺本さんに聞きました。霜が降りる条件
霜はどのような気象条件のときに発生しやすいのでしょうか。
寺本卓也さん
低気圧が去った後、中国大陸からやってくる移動性の大きな高気圧に覆われた日の翌日、時間帯は早朝に発生することが多いです。こういった日は、日中は雲一つない青空で、日差しのぬくもりを感じるいい天気です。しかし、夜になると気温が一気に下がります。雲がないことで、地上の暖かい空気がどんどん上空に逃げてしまう、放射冷却が起こるためです。そして気温が一番下がる夜明け前に、空気中の水分が凍って地上におり、霜になります。
放射冷却は、風が弱い日や空気が乾燥している日に強くなる傾向にあります。
放射冷却は、風が弱い日や空気が乾燥している日に強くなる傾向にあります。
霜害が起こる季節と地域
霜害が発生しやすい時季や地域、地形の特徴などはありますか?
寺本卓也さん
霜は秋から春にかけて、条件がそろえば発生します。
その中でも農産物にとって特に危険なのは4〜5月の間。というのも、この時季は葉が開き始める展葉期や果樹などの開花期にあたるためです。植物は芽の状態なら寒さに耐える力を蓄えています。しかし、展葉期以降、開花期に近づくほど、寒さに耐えることができなくなり、遅霜にあたると凍って枯れやすくなります。特に、気温が高めに推移し、農作物の生育が前進しているときなどは注意が必要です。
また、盆地、窪地、土手、防風林の近くなど、風の通り道がなく、冷たい空気がたまりやすい場所は霜害が発生しやすくなります。作物としては、りんごや柿、ナシ、ぶどうなどの果樹と、アスパラガス、じゃがいも、えんどうなどの野菜類、お茶、ムギ、タバコ、植林した樹木の苗木などが霜害の被害を受けやすいとされます。
その中でも農産物にとって特に危険なのは4〜5月の間。というのも、この時季は葉が開き始める展葉期や果樹などの開花期にあたるためです。植物は芽の状態なら寒さに耐える力を蓄えています。しかし、展葉期以降、開花期に近づくほど、寒さに耐えることができなくなり、遅霜にあたると凍って枯れやすくなります。特に、気温が高めに推移し、農作物の生育が前進しているときなどは注意が必要です。
また、盆地、窪地、土手、防風林の近くなど、風の通り道がなく、冷たい空気がたまりやすい場所は霜害が発生しやすくなります。作物としては、りんごや柿、ナシ、ぶどうなどの果樹と、アスパラガス、じゃがいも、えんどうなどの野菜類、お茶、ムギ、タバコ、植林した樹木の苗木などが霜害の被害を受けやすいとされます。
作物別!霜害の主な対策方法
 霜による被害を最小限に抑えるには、翌朝の予想最低気温や霜注意報など、気象庁が発表する気象情報に常に注意を払いつつ、予防のための事前対策をしっかりとすることが大切です。ここでは、基本的な対策法と作物ごとの対策についてご紹介します。
霜による被害を最小限に抑えるには、翌朝の予想最低気温や霜注意報など、気象庁が発表する気象情報に常に注意を払いつつ、予防のための事前対策をしっかりとすることが大切です。ここでは、基本的な対策法と作物ごとの対策についてご紹介します。霜害の対策
 霜害対策にはさまざまな方法があります。育てている作物や畑の環境と予想される低温の程度、コスト、労力などに合わせて、適切な対策を選びましょう。
霜害対策にはさまざまな方法があります。育てている作物や畑の環境と予想される低温の程度、コスト、労力などに合わせて、適切な対策を選びましょう。被覆法
寒冷紗や不織布、マルチなどの被覆資材や保温シートを使って作物を覆います。作物の上に棚を設置する「棚式被覆法」、支柱を弧状に立てる「トンネル式被覆法」、資材を作物に直接被覆する「直がけ被覆法」などがあり、使用する資材によって保温性が異なります、トンネル育苗やハウス栽培の場合は、ビニルを二重にすることも有効です。送風法
降霜時には、地表付近に比べて地上6~10m付近の気温が4~5℃高くなります。この上空のあたたかい空気を、ファンなどを使って作物の表面に吹き下ろすことで、霜害を回避する方法を送風法といいます。お茶やみかん畑で広く実施されていますが、上空の気温が-2℃以下になると効果がなくなる、防霜ファンの設置に費用がかかる、騒音がするなど導入には考慮すべき点があります。燃焼法
薪などを燃やして、発せられる熱で植物をあたためる方法。経費や設備投資が少なくすむ一方で、夜間の作業を伴うため作業者の負担が大きく、燃焼法を講じる農家は減少傾向にあるといわれます。散水氷結法
水が氷になるときに放出される潜熱(せんねつ)を利用して、霜を防ぐ方法です。スプリンクラーなどを利用して散水し、その水を凍らせることで植物体自体の凍結を防ぎます。気温が一定以下になると自動で散水を始めるスプリンクラーなどが、茶畑などで設置されています。煙霧法
煙や人工霧で放射冷却を少なくする方法で、盆地などに向いています。日没後できるだけ早く、くん煙作業を開始すると効果的です。機能性資材などの散布
葉面散布剤など、凍霜害を防ぐための機能性資材が販売されています。トレハロース糖類を含むものやコーヒー粕から取れるエキスを使ったものなどがあり、凍霜害が起こる時期に事前に散布する必要があります。霜が予想される日の数日前に散布すると効果的なので、気温の予測が大切になってきます。コーヒー粕を原料にした防霜資材が登場!そのメカニズムや実証試験の事例をチェック
コーヒー粕を原料にしたフロストバスターの詳しい製品情報はこちら
フロストバスター特設ページ購入希望・製品に関するお問い合わせはこちら
※「国内の農薬に関するお問い合わせ」を選択してください。
※「お問い合わせ内容」に製品名「フロストバスター」の記入をお願いします。
お電話でのお問合せ
※営業時間:平日9:00~12:00、13:00~16:30
じゃがいも
2月下旬〜3月に植え付ける春じゃがいもの場合、地中から出てきた芽が、遅霜にあたってしおれてしまうことがあります。また、11月に収穫期を迎える秋じゃがいもは、収穫間近で早霜にあたって地上部が枯れてしまうことも。こうした霜害を防ぐためには、寒冷紗や不織布を使ったトンネルの設置がおすすめです。加えて、秋じゃがいもの場合、いもが地表に出ないように土寄せをしっかり行うことも大切です。キャベツ
キャベツは比較的寒さに強い作物ですが、2月下旬~3月中旬に種をまく春まきの場合、発芽直後から本葉が出るまでは凍霜害を受けやすいので注意が必要です。ハウス内で育苗する、畝にトンネルを設置するなど、気温が15〜20℃になるように温度管理を行います。11月ごろ収穫期を迎える夏まきキャベツや冬を越す秋まきキャベツを霜から守る場合は、寒冷紗や不織布などの被覆資材を使った被覆法が用いられます。スナップエンドウ
スナップエンドウは、生育初期に一定の低温にさらされないと花芽が出ないため、越冬しての栽培が一般的です。比較的寒さに強い作物ですが、越冬時に生育が進みすぎていると霜害を受けやすくなるので、適期に播種することが大切です。その後は、支柱を弧状に立てる「トンネル式被覆法」を用いられることが一般的で、株の上に笹の枝やワラを被せるる昔ながらの方法も多く用いられます。ブロッコリー
ブロッコリーは寒さに強い作物で、一回の寒さや霜で枯れることはありませんが、複数回霜にあたると、葉が徐々に傷んで枯れたり、花蕾が付かなくなったりすることがあります。寒冷紗や不織布などの被覆資材を使ったトンネルを設置し、霜にあたらないようにすることが効果的です。レタス
冷涼な気候を好むレタスですが、2月下旬~3月中旬に種をまく春まきの場合は育苗期、秋まきの場合は結球期に凍霜害が起こりやすく、注意が必要です。ハウス内で育苗する、畝に寒冷紗や不織布などの被覆資材を使ったトンネルを設置するなど、被覆法での対策が一般的です。また、結球してから寒さにあたると味が落ちるので、霜がおりる前に収穫を終えるよう、栽培時期を調整しましょう。りんご
りんごは展葉期や開花期に遅霜が生じることが多く、霜の害を受けやすいため、万全の対策を講じる必要があります。燃料を燃やす燃焼法やファンを用いた送風法、スプリンクラーを使った散水氷結法が用いられるほか、霜溜まりを解消するなどの園内整備、花を複数残す摘花法の採用なども被害を最小限に抑えるのに有効です。予測と対策で作物を霜害から守る
 たった一度の霜害で、収穫ができなくなってしまう…そんなことは避けたいものです。霜害から作物を守るには、日頃から自分の畑や作物の特徴を知ることが大切です。気象情報をチェックし、畑の気温を予測して、適切な対策を実施しましょう。気象庁のウェブサイトには、2週間気温予報が掲載されています。また、民間の気象予報サービスを利用するのも一つの方法ですね。大切な作物を霜害から守りましょう。
たった一度の霜害で、収穫ができなくなってしまう…そんなことは避けたいものです。霜害から作物を守るには、日頃から自分の畑や作物の特徴を知ることが大切です。気象情報をチェックし、畑の気温を予測して、適切な対策を実施しましょう。気象庁のウェブサイトには、2週間気温予報が掲載されています。また、民間の気象予報サービスを利用するのも一つの方法ですね。大切な作物を霜害から守りましょう。Sponsored by アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社