目次
-
- AGRI PICK 編集部
AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む
トマト農家の仕事内容を知ろう

栽培の方法|ハウス栽培が76%
トマトの原産地は、ペルーやエクアドルがある南アメリカの北西部高原地帯とされています。そのため、乾燥した昼夜の温度差が大きい気候を好み、豊富な日照を必要とします。トマトの栽培方法には、露地栽培とハウス栽培がありますが、全生産量の76%がハウス栽培で生産されています。(参考:農林水産省「施設園芸をめぐる情勢」2020年1月)水耕栽培にも向いている
トマトは土で育てる土耕栽培のほか、水耕栽培にも適しています。水耕栽培は、こまめな肥培管理が必要になりますが、病害虫の発生リスクが少なく、施肥の管理がしやすいです。連作障害も発生しないため、安定的に生産できるというメリットがあります。具体的な栽培方法はこちらをチェック!
栃木県就農支援サイト「tochino-トチノ-」で児矢野さんの体験談を読む
トマト農家の仕事は大変?休みは取れる?
トマト農家の仕事が一番忙しいのは出荷の時期。トマトの食べごろを消費者に届くタイミングに合わせるため、毎日出荷作業を続けることがあります。露地栽培のトマト農家では、夏はほとんど休みがなく、冬に長期の休みを取るケースも。一方、ハウス栽培では、少しずつ栽培時期をずらして、年間を通して計画的に出荷できるよう調整していることがあります。
トマト農家に聞いてみよう!初期費用、魅力、将来性など
教えてくれたのは
 2016年に就農しトマトを栽培している梶原甲亮さんに、トマト農家になるために必要なことを教えてもらいました!梶原さんはAGRI PICKで連載記事を執筆しているほか、ブログでも発信を続けています。
2016年に就農しトマトを栽培している梶原甲亮さんに、トマト農家になるために必要なことを教えてもらいました!梶原さんはAGRI PICKで連載記事を執筆しているほか、ブログでも発信を続けています。梶原 甲亮さんプロフィール
1976年生まれ。九州大学法学部卒業後、熊本県庁に入庁。土木や農政、福祉などさまざまな業務に従事した後に退職し、2016年から就農。
ブログにはトマトの栽培に関することがたくさん掲載されているほか、仕事に対する想いなどが記されています。
「梶原耕藝」
梶原さんの就農体験談はこちら
梶原さんの記事はこちら
梶原さんはAGRI PICKでライターとしても活動しています。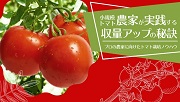
トマト農家になるのに必要な資材、設備、機械について教えてください

梶原甲亮さん
トマトを露地で栽培するか、ハウスで栽培するかによって分かれます。露地だとハウスなどの資材を必要としないぶん低コストでできますが、雨の多い日本では栽培期間は短くなるので、経営面を考えればハウス栽培がセオリーです。また、トマトに限らずですが、水耕栽培でない限りトラクターは必須です。
梶原さんのアドバイス:ハウスの資材や設備について
ハウス以外の資材や設備は、作型によっても異なってきます。夏秋作の場合は、主に雨よけ用のハウスや灌水設備があれば可能ですが、冬春作になると、2~3重のハウスのほか暖房設備なども必要となります。収量を増やそうと思えば、CO2施用機を使うこともありますが、いずれも化石燃料が必要なためコストがかかります。
新規就農の場合、必要な初期費用はどのくらいかかりますか?

梶原甲亮さん
施設野菜であるトマトを経営の柱にしようと思えば、それなりの初期投資は覚悟しなければいけません。初期費用として大きくのしかかるのはハウス導入費用です。近年は資材費が高騰しているため、ハウスの価格も上昇しています。
利用するハウスの種類によって、価格も大きく異なります。
利用するハウスの種類によって、価格も大きく異なります。
参考:梶原さんが購入したハウス
梶原さんが数年前に購入したハウスは、240万円/10a(間口=6m、奥行=40m、単棟、パイプ径=31.8mm、施工=自作)。ただし、仕様によって価格は大きく異なりますので、注意が必要です。
ハウスの導入には、単棟か連棟か、パイプの径はどの程度か、暖房・換気設備の有無、部材の運搬や施工をどうするのか(業者依頼 or 自作)などの検討項目があります。

梶原甲亮さん
非農家の方が新規就農で始める場合は農地の確保が必要かと思いますので、農地を買う(もしくは借りる)ための資金も必要です。
日射量や排水性などといった圃場環境は、栽培技術より作物の品質に大きく影響を与える場合が多いので、トマトに適した圃場かどうか慎重な見極めが必要になります。
日射量や排水性などといった圃場環境は、栽培技術より作物の品質に大きく影響を与える場合が多いので、トマトに適した圃場かどうか慎重な見極めが必要になります。
トマト農家の魅力はどんなところにありますか?

梶原甲亮さん
トマトは生産者の持つ技量や、圃場環境の影響などが如実に表れやすい作物です。
病害虫の予防や、水やり・追肥のタイミング、日射量や温度の管理などによって、収量に大きな差が出ます。裏を返せば、自分の持つ技量によって、目に見える形で大きな成果を生むことができる作物だといえます。
また、トマトは実が熟せば赤や黄など鮮やかに色づき、収穫してそのまま食べることもできるので、収穫体験を行ってもお客様からの評判がよく、観光農園を目指している方にも向いていると思います。
病害虫の予防や、水やり・追肥のタイミング、日射量や温度の管理などによって、収量に大きな差が出ます。裏を返せば、自分の持つ技量によって、目に見える形で大きな成果を生むことができる作物だといえます。
また、トマトは実が熟せば赤や黄など鮮やかに色づき、収穫してそのまま食べることもできるので、収穫体験を行ってもお客様からの評判がよく、観光農園を目指している方にも向いていると思います。
トマト農家の将来性をどのように考えていますか?

梶原甲亮さん
トマトは比較的安定した収入が見込める品目として認知されています。トマトのような施設園芸作物は、限られた圃場面積でも安定的に収益を得やすいのが利点です。私が農業を営んでいる熊本県山都町のような中山間地は、規模拡大が容易ではないため、施設園芸作物が適しています。夏秋トマトの産地は全国的に限られることから、今後も比較的安定的な取引価格が見込まれますが、近年の地球温暖化の影響もあり、夏場の高温対策も課題となっています。その点、冬春トマトは気候的に穏やかな時期にゆっくり育つので栽培しやすいといえます。また、トマトは自らの工夫しだいで高い付加価値を付けることも可能ですので、十分魅力的な品目といえます。
梶原さんのアドバイス:近年の市場価格について
近年の市場価格は冬春作を中心に低迷しています。低迷の理由は複数ありますが、一番の原因は「供給過剰」だと考えられます。トマト農家数の増加のほか、栽培技術の上昇などで出荷量が増え、結果的にトマトが市場で飽和状態になっていることが理由の一つです。特に冬春作は価格が上向かず心配な状況です。単体の農家としては収量を増やすことが収入増につながりますので、栽培技術を高め反収(作物の1反当たりの収量)を増加させることが目標になりますが、市場全体として出荷量が増えるとトマトの単価下落を招いてしまうという矛盾する状況も生まれています。
トマト農家はもうかる?年収が気になる!
 トマト農家の年収はどのくらいなのでしょうか?統計から粗利益を見てみましょう。
トマト農家の年収はどのくらいなのでしょうか?統計から粗利益を見てみましょう。| 品目 | 価格(円/Kg) | 10a当たりの収量(kg) | 10a当たりの粗利益(円) |
| トマト | 338 | 6,210 | 2,098,980 |
| ミニトマト | 626 | 5,840 | 3,655,840 |
2018年の青果物卸売市場調査によると、トマトの卸売価格は338円、ミニトマトは626円となっています。
圃場面積や販売先にもよりますが、例えば、農林水産省の作物統計調査によるとトマトの10a当たりの収量は全国平均で6,210kg、ミニトマトは5,840kgなので、10a当たりの粗利益はトマトで約210万円、ミニトマトで約370万円となり、1haの圃場があれば、その10倍となります。
ただし、梶原さんが話していたように、トマト農家の増加による競争の激しさや、施設園芸にかかるコストも考えておく必要があります。
トマト農家の多い地域

トマト栽培に向いている土地
トマトは高温多湿に弱い性質があるため、日本の温暖地では暑い時期に着色不良や病害虫の被害に遭うことが多いです。深くまで根を伸ばす作物のため、水はけがよく、地下水位が低い土地が好ましいです。土壌酸度は中性に近い酸性が最も適します。都道府県別トマト作付けランキング
トマトは全国的に栽培されていますが、圧倒的なシェアを誇っているのは熊本県。茨城県、北海道、千葉県でも多く栽培されています。| 都道府県 | 作付面積(ha) | 出荷量(t) |
| 熊本 | 1,250 | 128,800 |
| 茨城 | 882 | 41,100 |
| 北海道 | 814 | 56,200 |
| 千葉 | 759 | 28,700 |
| 愛知 | 490 | 41,000 |
熊本県で新規就農を目指すなら
トマト農家になるには

農業法人に就職。アルバイトから始めてみるのもOK
トマト農家になるには、トマトを栽培している農家や農業法人に就職して技術を習得するとよいでしょう。まずはアルバイトから始めてみるのも一つの方法です。農業に特化した求人サイトで情報をチェックしてみましょう。農業の求人専門サイト
法人への就職を経て独立就農した飯沼さんの体験談
研修に参加する。まずは知ることから
基礎からしっかりと技術を習得するなら、トマト農家を育てるための研修に参加するのも一つの方法です。トマトパークアカデミー
栃木県下野市の「トマトパークアカデミー」では、講義、実習、OJTにより、施設園芸分野でのスペシャリストを養成しています。北海道美瑛町 長期農業研修
北海道美瑛町は北海道のほぼ中央に位置する農業の盛んな町です。トマト栽培での新規就農を推奨しており、3~30日程度の短期農業研修で適性を確認したあと、2年間の長期農業研修を行うしっかりとしたプログラムを用意しています。しっかりとした準備が成功への道筋
 日本原産ではないトマトをビジネスとして生産するには、栽培に適した環境を準備することが必要です。トマト農家の梶原さんが教えてくれたように、トマト栽培に適した圃場やハウスを準備するとともに、研修などで栽培技術をしっかりと身につけることが成功への第一歩となるでしょう。サラダなど生食のほか、レシピの中で調味料のように使われることもあるトマトは、日本の食卓に欠かせない存在です。栄養素にも注目が集まっているので、トマト農家の可能性は今後も広がっていくのではないでしょうか。
日本原産ではないトマトをビジネスとして生産するには、栽培に適した環境を準備することが必要です。トマト農家の梶原さんが教えてくれたように、トマト栽培に適した圃場やハウスを準備するとともに、研修などで栽培技術をしっかりと身につけることが成功への第一歩となるでしょう。サラダなど生食のほか、レシピの中で調味料のように使われることもあるトマトは、日本の食卓に欠かせない存在です。栄養素にも注目が集まっているので、トマト農家の可能性は今後も広がっていくのではないでしょうか。























