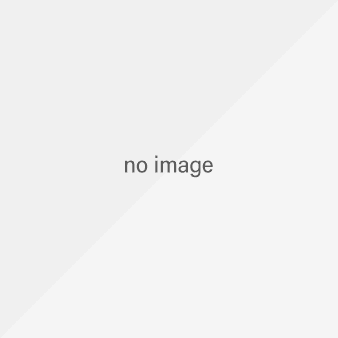目次
大根は、葉も丸ごと使ってみよう!
 つい先日家族で大根の畑へ行きましたが、畑は爽やかな緑色(葉っぱの色です)!根と茎(胚軸)にあたる白い部分が、数センチだけ地面からひょっこり顔を出しています。こちらの畑では、立派に育った大根を収穫させていただきました。ずっしりと重みのある葉付き大根、さてさてどんなふうに使いましょう。
つい先日家族で大根の畑へ行きましたが、畑は爽やかな緑色(葉っぱの色です)!根と茎(胚軸)にあたる白い部分が、数センチだけ地面からひょっこり顔を出しています。こちらの畑では、立派に育った大根を収穫させていただきました。ずっしりと重みのある葉付き大根、さてさてどんなふうに使いましょう。収穫した大根を眺めながら思うのは「大切に育てられたものは、大切にいただきたい」ということ。大根の葉っぱも余すところなく使いたいという気持ちになります。
大根の葉を使った、簡単養生ごはん<料理編>
 家庭菜園や畑などで収穫した大根だけでなく、最近は直売所やマルシェなどでも葉付きのまま売られている大根を見かける機会が増えました。その一方で「使い方がわからない」「家族が食べてくれない」などの理由で、葉をそのまま処分しているという声も時々聞きます。でも大根の葉にはβ‐カロテンやカルシウム、カリウムなどもたっぷり含まれていて、葉も丸ごといただくことで栄養もしっかりと摂取できます。そこで、大根の葉の下処理方法と簡単な食べ方をご紹介したいと思います。
家庭菜園や畑などで収穫した大根だけでなく、最近は直売所やマルシェなどでも葉付きのまま売られている大根を見かける機会が増えました。その一方で「使い方がわからない」「家族が食べてくれない」などの理由で、葉をそのまま処分しているという声も時々聞きます。でも大根の葉にはβ‐カロテンやカルシウム、カリウムなどもたっぷり含まれていて、葉も丸ごといただくことで栄養もしっかりと摂取できます。そこで、大根の葉の下処理方法と簡単な食べ方をご紹介したいと思います。大根の葉の下処理(あく抜き)の方法
 収穫したら早めに、包丁などで切って根の白い部分と葉の部分にわけ、下処理をしておきます。葉が付いたまま置いておくと、傷みが早くなってしまうので注意してください。
収穫したら早めに、包丁などで切って根の白い部分と葉の部分にわけ、下処理をしておきます。葉が付いたまま置いておくと、傷みが早くなってしまうので注意してください。〈材料〉作りやすい分量
・大根の葉 1本分
・塩 ひとつまみ
作り方
1.大根の葉に付いた土などをよく洗い落とす。鍋に湯を沸かし、塩と大根の葉を入れて1~2分程度ゆでる。2.1の葉を水にさらして、あく抜きをする。
3.2の葉はしっかりと水気を絞る。根の近くの筋張った固い部分は切り落とし、約1cm幅に刻む。
ポイント
・冷蔵庫に入れて、数日以内に使うようにします。・すぐに使わない場合は、小分けにして冷凍保存すると便利です。使う時は半解凍して、炒めものやスープなどに入れます。
まずはシンプルに食べてみよう
 大根の葉の下処理が終わったら、まずはシンプルに味わってみましょう。我が家ではポン酢とかつおぶしなどと組み合わせて、即席のお浸しや和え物にすることが多いです。このほか、柚子の千切りを加えて浅漬けなどにするのもおいしいです。
大根の葉の下処理が終わったら、まずはシンプルに味わってみましょう。我が家ではポン酢とかつおぶしなどと組み合わせて、即席のお浸しや和え物にすることが多いです。このほか、柚子の千切りを加えて浅漬けなどにするのもおいしいです。大根の葉を使った簡単養生ごはん
大根の葉はいろいろな料理に活用できます。葉には繊維が多いので苦手な子どもも多いですが、ごはんやスープなどに混ぜたり、甘辛味に味付けしたりすると食べやすくなります。菜飯ごはん
 炊き立てのごはんに、下処理をして細かく刻んだ大根の葉と塩を混ぜ合わせた一品です。緑色が爽やかで、色も香りも食欲をそそります。まずは大根の葉を少量混ぜ込んでみましょう。私の暮らす愛知県の郷土食のひとつとしても知られており、豆腐田楽などと一緒にいただくことも多いです。
炊き立てのごはんに、下処理をして細かく刻んだ大根の葉と塩を混ぜ合わせた一品です。緑色が爽やかで、色も香りも食欲をそそります。まずは大根の葉を少量混ぜ込んでみましょう。私の暮らす愛知県の郷土食のひとつとしても知られており、豆腐田楽などと一緒にいただくことも多いです。大根の葉のふりかけ
 下処理をした大根の葉を、ごま油などで香ばしく炒めて、醤油・みりん・酒で甘辛く味付けします。手軽に作れる昔ながらの保存食のひとつで、ごはんがどんどん進みます。豆腐や厚揚げなどにトッピングして食べるのもよく合います。
下処理をした大根の葉を、ごま油などで香ばしく炒めて、醤油・みりん・酒で甘辛く味付けします。手軽に作れる昔ながらの保存食のひとつで、ごはんがどんどん進みます。豆腐や厚揚げなどにトッピングして食べるのもよく合います。大根の葉のポタージュスープ
 下処理をした大根の葉を使ったポタージュスープは、とろみがあり食べやすい一品です。みじん切りにした玉ねぎや長ねぎなどのネギ類を油で炒めてから、里芋やじゃがいもなどの芋類と大根の葉、水を加えて煮込みます。柔らかくなったら火を止めて、粗熱が取れたころにミキサーなどでなめらかになるまで攪拌します。
下処理をした大根の葉を使ったポタージュスープは、とろみがあり食べやすい一品です。みじん切りにした玉ねぎや長ねぎなどのネギ類を油で炒めてから、里芋やじゃがいもなどの芋類と大根の葉、水を加えて煮込みます。柔らかくなったら火を止めて、粗熱が取れたころにミキサーなどでなめらかになるまで攪拌します。まだまだある!大根の葉の活用法<暮らし編>
 大根の葉はおいしいのでぜひ料理に使いたいですが、鮮度が落ちている場合や、大量にあって料理に使いきれない場合などは入浴剤にすることもできます。大根の葉を干したものを使ったお風呂は「干葉湯(ひばゆ)」と呼ばれ、民間療法などでは全身浴ではなく腰まで浸かる「腰湯用」として、冷え対策や婦人病予防などに使われてきました。
大根の葉はおいしいのでぜひ料理に使いたいですが、鮮度が落ちている場合や、大量にあって料理に使いきれない場合などは入浴剤にすることもできます。大根の葉を干したものを使ったお風呂は「干葉湯(ひばゆ)」と呼ばれ、民間療法などでは全身浴ではなく腰まで浸かる「腰湯用」として、冷え対策や婦人病予防などに使われてきました。少し手間はかかりますが、寒い日にこの干葉湯に入るとポカポカと身体が温まります。自然食品店などでは「大根干葉湯」の市販品を見かけることもあります。まずは市販品を試して、どんなものかを手軽に体験してみるのもいいかもしれません。
入浴剤、干葉湯の作り方をご紹介します。
大根の葉を使った入浴剤、干葉湯の作り方
大根の干葉湯に必要な材料は、大根の葉と自然塩だけ。余分なものを加えず材料がシンプルなので安心して利用できるのも魅力のひとつ。自然の恵みを体いっぱいに感じることができます。〈材料〉1回分
・大根の葉 2本分
・水 2リットル
・自然塩 大さじ1~2(ひとにぎり)
作り方
1.大根の葉は、カラカラに乾燥するまで天日干しにする。2.1の大根の葉と水、自然塩を鍋などに入れて火にかける。沸騰したら弱火にして、茶色くなるまで煮出す。
3.湯船に2の煮汁を全て入れれば、できあがり。
ポイント
大根の葉は煮出さずに、布袋などに入れて湯船に浮かべて使用することもできます。大根の葉を煮出した方が成分がしっかり抽出できますが、干葉湯を手軽に試したいという時には便利です。観葉植物として眺めて楽しむ方法も
 白い部分を残して切った大根の葉は、水に浸しておくと再び生長していきます。冬場の貴重なグリーンとして、観葉植物のように眺めて楽しむという方法もあります。
白い部分を残して切った大根の葉は、水に浸しておくと再び生長していきます。冬場の貴重なグリーンとして、観葉植物のように眺めて楽しむという方法もあります。室内で使えるおしゃれなプランターには、いろんな種類があります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
食材の大切さを感じる、おすすめの絵本をご紹介!
 家庭菜園などを通して身近な野菜を育てたり、旬の野菜を丸ごと味わったりする喜び。大根の葉を無駄なく活用することは、こうした喜びをさらに増幅させてくれます。
家庭菜園などを通して身近な野菜を育てたり、旬の野菜を丸ごと味わったりする喜び。大根の葉を無駄なく活用することは、こうした喜びをさらに増幅させてくれます。私ごとですが、今年はコロナ禍による外出自粛の影響などもあり、自宅の小さな庭で野菜や果樹を育てたり、収穫して料理をしたりして楽しむ時間が増えました。また幸運なことに、自宅近くに本格的な農業を営んでいる畑などもあり、旬の時期には収穫体験などを通して自然の恵みを全身で感じています。
お気に入りの絵本『げんきなやさいたち』
家庭菜園や畑で過ごしていると、意外な発見がたくさんあります。そんな発見が詰まったお気に入りの絵本「げんきなやさいたち」をご紹介しますね。現在は絶版になっているようですが、図書館や古本屋、Amazonなどで手に取ることができます。よくよく観察してみると、野菜の姿や形はとってもユニーク。この絵本では、虫たちと共生しながらのびのびと育ついろんな種類の野菜が描かれており、あふれんばかりの生命力を感じます。もちろん大根の姿も描かれています。身近な野菜は、自然の恵みそのもの。私たちは、その恵みをどんなふうに受け取っていきましょうか。
『もったいないばあさん』から学ぶこと
また、食材を大切にいただく「おばあちゃんの知恵」を子どもにもわかりやすく紹介した絵本「もったいないばあさん」もおすすめの一冊です。大人気の絵本シリーズでアニメ化もされているので、ご存知の方も多いと思います。「もったいない」ってどういう意味?「米粒を残さない」など、ものを大切にする教えが、もったいないばあさんとの対話によってコミカルに描かれています。我が家では2才になる息子に「もったいないばあさんがやってくるよ~」といいながら食事をすることもしばしば。それだけに大根の葉をいかに上手に活用するか、自身の力量が試されます(笑)。
大根を丸ごと使うと、心も身体も気持ちがいい!
 大根は白い部分だけでなく、葉も料理や入浴剤などに余すところなく活用することができます。食養生の考え方では「一物全体食(いちもつぜんたいしょく)」という考え方があり、食材を丸ごといただくことはバランスが取れているとされています。そして実際に、丸ごと大切にいただいてみると、体だけでなく心もじんわりと満たされていくことに気が付きます。
大根は白い部分だけでなく、葉も料理や入浴剤などに余すところなく活用することができます。食養生の考え方では「一物全体食(いちもつぜんたいしょく)」という考え方があり、食材を丸ごといただくことはバランスが取れているとされています。そして実際に、丸ごと大切にいただいてみると、体だけでなく心もじんわりと満たされていくことに気が付きます。大根の葉も無駄なく活用して、心も身体も気持ち良く過ごせますように。
家庭菜園での大根の栽培方法については、こちらの記事をご覧ください。
大根など冬野菜のおいしい保存方法については、こちら。