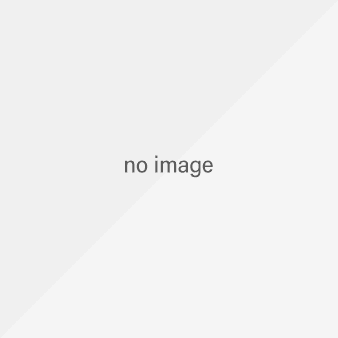-
 ライター
ライター - 紀平 真理子
オランダ大学院にて、開発学(農村部におけるイノベーション・コミュニケーション専攻)修士卒業。農業・食コミュニケーターとして、農業関連事業サポートやイベントコーディネートなどを行うmaru communicate代表。
食の6次産業化プロデュ ーサーレベル3認定。日本政策金融公庫農業経営アドバイザー試験合格。
農業専門誌など、他メディアでも執筆中。…続きを読む

写真提供:久松達央
【新規就農者や、すでに営農しているもののつまずいてしまっている人へ】 株式会社久松農園 久松達央さんによる、豊かな農業者になるためのメッセージを伝える連載。 オーガニックな方法で農産物を栽培する生産者の中には、「有機だから安全」「有機だからおいしい」「有機だから環境にいい」とうたっている人もいますが、有機農業に取り組む久松農園の久松さんは、それらはすべて世の中の人が持っている有機農業やオーガニック農産物に関する誤ったイメージだと指摘します。第10回は、「有機農業の3つの誤解」について解説してもらいました。 
写真提供:紀平真理子
プロフィール 株式会社 久松農園 代表 久松達央(ひさまつ たつおう) 1970年茨城県生まれ。1994年慶應義塾大学経済学部卒業後、帝人株式会社を経て、1998年に茨城県土浦市で脱サラ就農。年間100種類以上の野菜を有機栽培し、個人消費者や飲食店に直接販売。補助金や大組織に頼らない「小さくて強い農業」を模索している。さらに、他農場の経営サポートや自治体と連携した人材育成も行っている。著書に『キレイゴトぬきの農業論』(新潮新書)、『小さくて強い農業をつくる』(晶文社)
有機野菜だから安全でおいしくて環境にいい?

写真提供:紀平真理子
「有機」や「オーガニック」という言葉は、「安全」「おいしい」「環境にいい」というフレーズと一緒に使われることが多く、消費者だけでなく生産者の中でもそのように認識している人がかなりいます。まずは、久松さんの考える「有機」について話を聞きました。
有機農業は世の中に誤解されている
有機野菜は安全で、おいしくて、環境によくて…いいイメージがありますよね。
すべて正しくありません。僕は、「有機だから安全」「有機だからおいしい」「有機だから環境にいい」というのは、有機農業に対する間違ったイメージだと考えています。今回は、有機農業が誤解されている3つのことについて話します。
誤解1|有機だから安全?

写真提供:久松達央
一つ目の誤解である「有機だから安全」について解説してもらいました。化学合成農薬(以下「農薬」)や化学肥料を使用した一般的な慣行農業と比較して、農薬や化学肥料を使わない有機農業の方が安全だといわれることがよくありますが、これは本当なのでしょうか。 ※「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に則った場合、農薬を使用していないと「農薬:栽培期間中不使用」ですが、本文中では「無農薬」と表記します。
有機野菜は慣行野菜と同程度に安全
有機は農薬を使っていないので安全ですよね。
有機野菜は安全です。適正に農薬を使っている慣行農業でつくった野菜と同じ程度に安全です。
同じ程度なのですか。農薬は危険だと思っていました。
今の農薬は大変に厳しい基準で管理されており、食べる人が農産物を口にする時点で農薬が残留していること自体がまれです。万が一残留があった場合でも、それが人の健康を害することがないレベルに使用がコントロールされています。現在の日本の農業における農薬の使用が、食べる人の健康を害することはあり得ないといって問題ないと思います。「農薬は危険だ」という主張が繰り返されていますが、科学的に根拠がないものばかりです。
参考:内閣府食品安全委員会事務局
「食品安全委員会における農薬の食品健康影響評価について」「無農薬は身体にいい」と安全をうたっている生産者もいますよね。
農薬を使用している農産物が健康に害がないのですから、農薬を使っていないからといって身体にいいという理屈は成立しません。これはウソだといっていいでしょうね。そもそも「○○は身体にいい/悪い」という表現自体がおかしなものです。自然のものも含めてすべては毒になり得ます。塩にも水にも致死量はあります。ある物質が毒になるか否かを決めるのは摂取する量です。毒性の高いものは少量でも毒になりますし、毒性の低いものは大量に摂取しないと害を及ぼしません。なので、「○○という物質は、△△の量を摂ると、××のリスクがある」が正しい表現ですね。
参考書籍
お母さんのための「食の安全」教室
著者:松永 和紀
出版社:女子栄養大学出版部
発売年:2012年
食べものの中身を心配するのは先進国だけ
それでも、長生きしたいので無農薬の野菜を食べています。
素晴らしいですね。じゃあ僕より寿命が15分伸びますね。
え、たったそれだけなのですか。
損失余命といって、さまざまな危険の原因にさらされることによって、その後の死亡率が高まり、その結果失う平均余命を算出して比較する考え方があります。例えば、タバコを危険の原因とすると、タバコを摂取することで、してない人に比べてどれだけ命が短くなっているか、死亡率や発がん性の発生確率などから逆算して考えます。推定値なので厳密な比較ではありませんが、リスクの大小をざっくり捉えるためには役に立ちます。残留農薬の場合は、過大に見積もっても損失余命は0.01日、つまり15分弱との算出もあります。
命を短くする原因は農薬ではないのですか!
世界全体を見れば、今でも死因のトップは飢餓、つまり栄養不足なのです。日本で見ると、がんや心臓疾患、喫煙、アルコール、自殺などが死因の上位です。残留農薬などを心配しているのは、先進国の、しかもごく最近の話です。本当に長生きしたいなら、残留農薬を気にし過ぎるより、タバコやお酒を控えて、心身ともに健康に生活することですね。政府も有機農業の拡大などにお金を使うより、自殺対策に取り組んだ方が、僕は効果的だと思っています。
安全と安心は違う
有機野菜だから安全というわけではないのですね。「安全・安心な有機野菜」という表現が多用されるのはなぜですか。
有機であろうがなかろうが、農産物は安全です。でも、安全であることが安心につながっていない人もたくさんいます。そもそも「安全」と「安心」は違います。科学は「安全」を説明できますが、直接「安心」を与えることはできません。自分が「安心」できないからといって、科学的な客観的事実である「安全」を認められなかったり、攻撃することは無意味です。「安心」についてはそれぞれの感受性によるものなので、これを非難することも意味がありません。
安全と安心の違い 安全:客観的。科学的根拠や客観的事実に基づく「材料」や「道具」 安心:主観的。自分で解釈してどう感じるかに基づく「自分という器」
誤解2|有機だからおいしい?

写真提供:紀平真理子
二つ目の誤解は、「有機だからおいしい」です。「有機だから」だけでなく、「オーガニックだから」「無農薬だから」おいしいというキャッチコピーもよく目にしますが、これも正しくないと久松さんは言います。それは、野菜のおいしさを決める三要素を満たしていれば、栽培方法に関係なくおいしい野菜を育てることができるからです。
久松さんの野菜は、有機だからおいしいですよね。
え?そうなんですか?私が食べたほかの有機野菜もおいしかったです。なぜでしょうか。
僕は、野菜のおいしさを決める三要素は「鮮度」「品種」「栽培時期」だと考えています。もし、ある有機農家の野菜がおいしいのであれば、その人は結果的にこの三要素が十分に満たされているのでしょうね。栽培が有機であるかどうかとは直接の因果関係はありません。
久松流|おいしさの三要素 鮮度:収穫から消費者に届くまでの時間が短い 品種:流通や栽培が難しくてもおいしい品種を選定する 栽培時期:旬の時期に栽培する
もう少しわかりやすく説明してください。
因果関係と相関関係の違いです。「朝ご飯を食べている子は成績がいい」という場合に、「朝ご飯を食べている子」は「規則正しい生活をしている」や「親の収入が高い」などさまざまな要素が絡み合っていて、結果的に「成績がいい傾向がある」にすぎません。朝ご飯そのものが成績に関連しているわけではないですよね。それと同じで、有機野菜が結果的に上の三要素を満たすおいしい野菜になっていることは考えられますが、「有機だから」おいしいという直接の因果関係はありません。
有機野菜は栄養価も高いといわれていますが、自然由来の肥料を使っているからでしょうか。
植物が「これは有機肥料だ、吸おう」とか考えるわけないですよね。有機肥料とか無肥料は人間である生産者の行為を示しているだけで、植物の側に立つとどうでもいいことです。人間の食べもので例えると、「コラーゲンを食べてお肌ぷるぷる」とかいいますけど、ただのタンパク質なので大豆でも同じです。コラーゲンにはお肌ぷるぷるを構成する要素はあるかもしれないけれど、ほかのものでもいいわけです。堆肥などを使う有機農業と化学肥料を使う慣行農業も、その程度の違いです。
それはどういうことですか。
何かの道具や手法でないと再現できないというのは間違いで、有機でできることはほかの手法でも再現できるということです。「macじゃないといい小説が書けない」といったら、皆おかしいことにすぐに気づきますが、「有機じゃないとおいしくて栄養価が高い野菜はできない」も同じくらいおかしいです。
栽培手法でモノは変わらないということなのですね。
有機栽培だからおいしい野菜を育てられていると思っている人も、実は別の理由でおいしいものができているだけかもしれません。三要素を満たしていなければ、有機でもおいしくないものはたくさんありますし、三要素をおさえていれば、慣行栽培でもおいしいものもたくさんあります。ひとつの栽培方法でしか同じものが再現できないということはありえません。
誤解3|有機だから環境にいい?

写真提供:久松達央
三つ目の誤解である「有機だから環境にいい」についてもお話を聞きました。「有機農業は農薬を使っていないので環境に配慮している」ということについて、「農薬不使用=環境にいい」とは一概にはいえないと久松さんは話します。それは、畑や田んぼの中だけの視点ではなく、生産者が使用する農業資材の原料調達、生産、流通、廃棄などすべての工程における環境負荷を考える必要があるからです。
有機が環境にいいとは一概にはいえない
有機農業は環境にやさしいですよね。
それもケースバイケースですね。期待に沿えずすみません。環境問題といっても広範囲で複雑多岐にわたります。有機だからあらゆる側面で環境負荷が低いとはいいがたいです。
農薬の使用量を減らせば環境にいいと思うのですが、いかがでしょうか。
それも、一概にはいえないんですよ。例えば、稲作では紙マルチ栽培という技術があります。最初に田んぼを紙で覆い、そこに苗を植えていくので、紙が光を遮り雑草が生えるのを防ぎます。農薬の一つである除草剤をゼロにできるので、紙マルチ栽培は環境にやさしく見えますよね。でも、紙マルチ栽培は、除草剤を使った慣行農業と比べても、二酸化炭素を排出量が突出して多いのです。というのも、紙の製造工程で大量に二酸化炭素を排出しているからなんです。
では、紙マルチが環境に悪いということですか。
そうではありません。除草剤を使わないことを評価するのか、二酸化炭素を排出しないことを評価するのかということですね。「紙マルチ栽培=環境負荷が低い」と一概にはいえないことが難しいところです。
野菜の有機栽培の場合は、除草剤を使わず草刈りをするので環境にいいのではないでしょうか。
そうですといいたいところですが、これも必ずしも環境にいいとはいえません。除草剤を使わないので、管理機を使ってかなりの回数で除草をしています。そうなると、管理機を動かすために必要な化石燃料を使っていることをどう評価するのか。個々の条件で変わってくるので、これも一概に有機の方がいいとはいえません。農業と環境の問題は、正しそうなことほど、精緻な検討が必要ないい例だと思います。
久松さんが有機農業に取り組む理由

写真提供:久松達央
「有機だから」という理由で、農産物の安全やおいしさ、環境への配慮を担保できず、顧客へのアピールポイントにならないのであれば、久松さんはなぜ有機農業に取り組んでいるのでしょうか。また、有機農業と安全!おいしい!環境にやさしい!に因果関係がないことを断言してしまうことで、久松農園の経営に影響を与えてしまわないのでしょうか。
有機に取り組むのは己の美学によるもの
なぜ久松さんは有機農業をやっているのですか。
今は、農薬や化学肥料だけでなく、新しい品種など栽培上のリスクを避けるためのさまざまな「武器」が使えます。ただ、そのような技術に頼り過ぎてしまうと、「本当の旬がいつなのか」「健康な野菜とは何なのか」ということが見えにくくなってしまいます。僕が有機農業をするのは、そのような「武器」を放棄することで本質的な問題を見つめ、モノを見る目を育てたいからです。有機農業は、人を育てる方法だと思っています。難しくて、意義があることってかっこいいじゃないですか。武器ではなく頭を使って工夫で課題を解決したい、これが自分のこだわりなんです。
有機を否定して商売に影響はないのでしょうか。
そもそも「有機や無農薬だから安全・おいしい・環境にいい」ということを売りにしていないので、全く影響ありません。
久松理論|有機農業の3つの誤解

写真提供:紀平真理子
有機農業だから安全、おいしい、環境にいいという有機農業の3つの誤解について、久松さんに解説してもらいました。
誤解その1:有機だから安全|正しくは有機は慣行と同程度に安全
有機農産物は慣行農産物と同程度に安全。農薬などの化学物質だけでなく、すべてのものは「量」で影響を与えるかどうかが決まり、量は厳しく管理されています。そのため、科学的な客観的事実として農薬は「安全」ですが、個人の感性として「安心」できるかどうかはまた別の話です。
誤解その2:有機だからおいしい|三要素を満たせば、栽培方法を限定せずおいしい野菜はできる
おいしさの三要素である「鮮度」「品種」「栽培時期」を満たせば、有機栽培や慣行栽培などの手法に限らずおいしい野菜を育てることができます。「有機だからおいしい」は、「macだからいい小説が書ける」というくらいロジックが成立していません。
誤解その3:有機だから環境にいい|製品のライフサイクル全体を見て、何を評価するのか
有機栽培という一つの農法や、一つの農業資材がすべてにおいて環境にいいというのは正しくありません。何を評価するかによって「環境にいい」は変動します。また、農業現場だけでなく、資材の生産から廃棄までの一連の流れの中でどのように環境に影響を与えるかという視点も持たなければいけません。
もっと知りたい人はこちら
キレイゴトぬきの農業論
著者:久松達央
出版社:新潮社
発売年:2013年
バックナンバーはこちら
久松達央さんのジツロク農業論