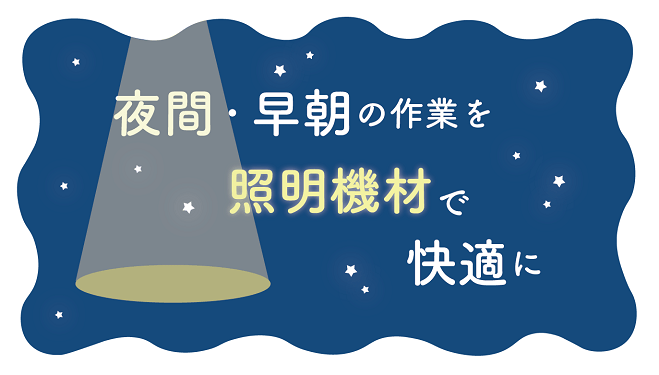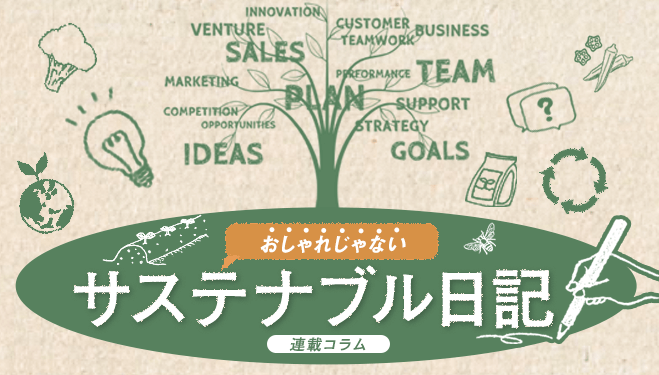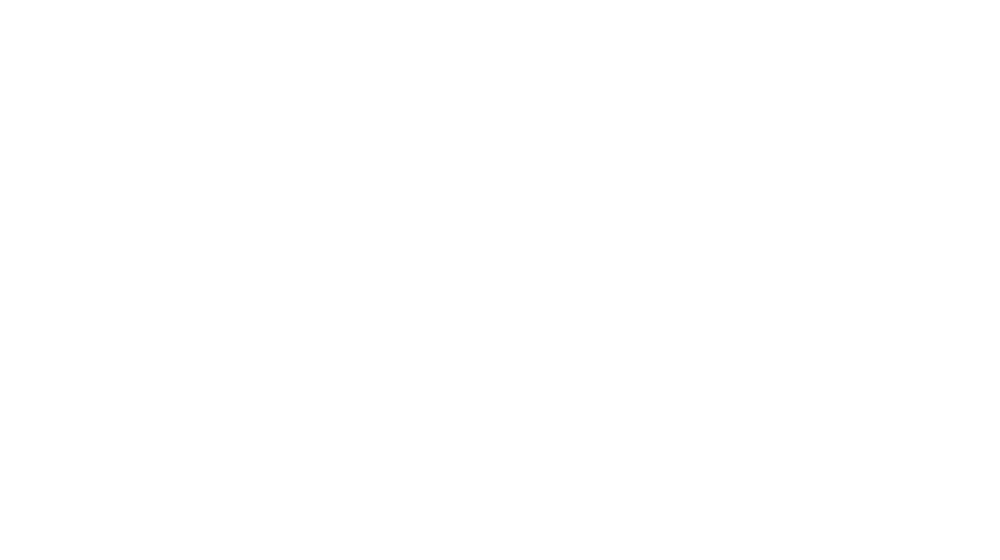長野県佐久市に所在する株式会社J’Pumpkin(ジャ・パンプキン)は、「佐久地域の農地を次世代につなぐ」という理念を掲げ、それを実現する手段として、カボチャの大規模栽培を選択。「佐久をカボチャの産地にする」という大きな目標を達成するため、農業法人を設立しました。
若手農家として何をすべきか
始まりは有機農家
J’Pumpkinの代表取締役・大塚 悠さんの実家は地元の有機農家。大学卒業後、実家に戻った大塚さんは、父・献三さんのもとで就農します。献三さんは、地域の有機農家と生産組合「佐久ゆうきの会」を立ち上げ、共同出荷、有機JAS認証の取得、野菜の規格を統一、生協と組んで販路を拡大と、新しい形の有機農業に取り組んでいました。

現在、「佐久ゆうきの会」は16名の会員から成る有機JAS農家の集団に成長。その中心は20〜40代の若手農家で、大塚さんは副会長を務めています。
農業経営塾で視点が変わる
有機農家になって3年目の25歳のとき、大塚さんは長野県が主催する農業経営勉強会「信州農業MBA」を受講します。受講の目的は「有機農家として経営を向上させる」ことでした。
講義が進む中で、大塚さんは担い手の高齢化と後継者不足、耕作放棄地の増加といった農業の課題と直面します。そして、自分たちの農業から地域の農業へと、視野が広がったと話します。

佐久をカボチャの産地にする!?
カボチャなら戦える
佐久市内の農地面積は約6,000ha。その3分の2は水田、3分の1が畑です。今後、就農人口が減って管理しなければならない面積が増えることを考えると、「法人化、大規模化は当然の流れ」と大塚さん。では、大規模化に適した作物は何か?そう考えて大塚さんが選んだのが、カボチャでした。

カボチャを選んだ理由は、もう一つあります。カボチャは収穫に機械を使えないため、すべて手作業になります。それは、カボチャの世界的な産地であるニュージーランドでも、国内有数の産地・北海道でも変わりません。

仲間2人でスタート
2013年、26歳のとき、大塚さんは経営塾で意気投合した若手農家と2人でカボチャ栽培に乗り出します。このとき掲げた目標は「佐久市でカボチャ100ha栽培」という大きなものでした。

グループ名は「国産カボチャの需要を高めよう」という意味を込めて「J‘Pumpkin」に決定。大塚さんたちは手探りしながら、農地の取得、栽培技術の確立、販売先の開拓、アルバイトの募集など、少しずつ歩みを進めていきます。
農地探しは、農協や自治体の仲介、知人の紹介からスタート。最初は、「見知らぬやつらがカボチャを植えている」と警戒されることも。しかし、真面目に働く姿が認められ、地主さんから「うちの畑もやってよ」と声がかかるようになって畑は増えていきました。
栽培技術については、カボチャ専業農家が地域にいないため、北海道や茨城などの産地に出向いて勉強。栽培面積が増えてくると、種苗メーカーが興味を持ってくれ、育種担当者が栽培指導に訪れるようになりました。
ロットが大きくないと儲からない
販売先は、経営塾の講師や父親の人脈を頼ったり、地元のスーパーに飛び込み営業をしながら開拓していきました。その当時からの取引先は5〜6社ありますが、すべて契約栽培または市場への出荷です。

「カボチャは儲からない」と農家はぼやくといいますが、大塚さんに言わせれば、「買う側に必要な量をそろえていなければ商売にならない」。数をそろえるためには、産地から集めてくるほかなく、必然的に流通は農協、市場経由となるわけです。

売上3,000万円で法人化に踏み切る
法人化の一番の目的は人材獲得
仲間と2人で始めた1年後、大塚さんの地元の同級生で、実家が米農家という宮澤祐貴さんがJ‘Pumpkinに合流します。2018年4月、メンバー3人が資本金300万円を出資して役員に就任。J’Pumpkinは農業法人を設立しました。

設立の手続きは、自分たちで書類を書き、行政書士に仕上げをしてもらって、すんなりと終わったといいます。「法人成り」(個人で行っていた事業を新会社が引き継ぐこと)でしたので、「付き合っていて結婚しました、みたいな感覚」と笑います。
法人化のメリット・デメリット|デメリットはなかった
法人化による変化は、「自分の考えていること、想像していることを、他人と共有する」ことだと大塚さん。

同時に、従業員の意思も尊重しています。

個人事業と会社組織では、中身が大きく異なります。就業規則、給与体系、福利厚生などの制度を作り、明文化したこと。これが、家族経営の農家と農業法人との一番の差だと大塚さんは話します。

今後は多角化経営も視野に
健全な土壌を作りながら
2020年4月で3期目を迎えたJ’Pumpkin。栽培面積は30ha、収量は250t、売上は5,000万円と順調に成長を続けています。会社の理念に共感する若手も採用し、来春には正社員が3人に増える予定です。一方、設立メンバーだった一人が抜け、役員は今、宮澤さんと2人になりました。
栽培面積の目標は400haに変更しました。次なる一手は「タマネギと米の栽培」と大塚さん。カボチャ単作での事業拡大には限界があり、今後は多角化を目指します。理由の一つはキャッシュフローの問題です。カボチャ販売からの入金は8月から1月まで。その後、半年間を埋める品目が必要なのです。
また、カボチャの単作には連作障害という問題もあります。タマネギの栽培は、連作障害を防ぐのも目的です。一方、米を導入するのは、佐久はもともと水田に適した地域なので、カボチャに転作できない場所もあるからです。今後、広い農地を管理していくことを考えると、田んぼのまま残す方が管理しやすいという読みもあります。

地元を巻き込んで
J’Pumpkinの仕事ぶりを見て、地元でカボチャ栽培に関心を示す農家も増えてきました。個人農家にカボチャを栽培してもらい、J’Pumpkinが買い取る仕組みも構築。現在、協力農家は7軒を数えます。高齢の農家から「うちのカボチャ、買ってくれるかい?」と尋ねられることも。カボチャ産地化の計画は、狙い通りの広がりを見せています。

目的とする事業をそのまま法人化という形にしたJ’Pumpkin。単なる規模拡大ではなく、理念をもって事業を拡大し、地域や農業全体の発展を意識した経営の例といえるでしょう。
農業法人情報(2020年10月現在)
・名称:株式会社J’Pumpkin(ジャ・パンプキン)
・所在地:長野県佐久市
・法人設立:2018年4月
・資本金:300万円
・従業員数:10名(役員2名)
・栽培面積:30ha
・栽培品目:カボチャ
・収穫量:250t
・売上高:5,000万円
・販売先:市場経由、卸業者
連載「農業法人を設立するには?」バックナンバーはこちら。